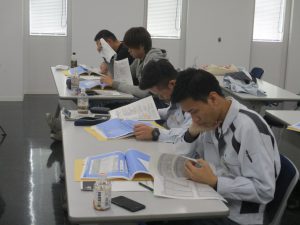11月11日(月曜日)訓練▲日目
昨日、一昨日と訓練校鉄筋コースは初の連休でしたが、この2日は過半数の大阪から参加の訓練生には「帰省日」であり、また東京を含む東日本から参加の訓練生にとっては「移動日」でもありました。
第5週の月曜の訓練は、京阪電車の樟葉(くずは)駅に朝8時半に集合です。
なぜまた東京からはるばる大阪へ?・・・というと、ここには大林組の西日本ロボティクスセンター(旧称:大阪機械工場 以下「西日本RC」)があり、鉄筋工なら一日中絶叫(?)していられる『配筋検査テーマパーク』があるのです。
冗談はさておき(まんざら冗談でもありませんが)、去年もここに日帰り弾丸ツアーを挙行したのですが、その時はいかんせんすべてのアトラクション・・・いや模擬配筋検査台をこなすのに十分な時間が取れずに、いい試合をしたものの日没コールド、みたいな消化不良気味になってしまいました。
そこで今年は、週末を利用して前日乗り込みの上、朝から丸一日を使ってとことん配筋検査三昧をやろう!という趣向で臨みます。
そのために、先の木曜日に半日をかけて検査対象物(1スパン四方の鉄筋モックアップ=模擬検査台)の図面レビューを行なってもいるのです。
大阪の北浜および京阪線の樟葉駅で訓練生・講師全員遅れずに合流して現地に向かいます。
![IMG_3881[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/11/IMG_38811-300x225.jpg)
到着後、研修室で朝礼とラジオ体操をいつも通りやって、ブリーフィングを行いさっそく配筋検査へ。
![IMG_3892[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/11/IMG_38921-300x225.jpg)
実際にこれを見て絶叫?したのは、安藤講師が「うわぁ〜!」。 見る人が見れば唸ります。
先々週の埼玉の東日本RCのモックアップは1台で45分検査にかけました。こちらは4台ですが9時半からまだまだたっぷり時間はあります。
結局、『せっかく遠路来たんだから、訓練生には気の済むまでモックアップに向き合ってもらおう。鉄筋の基本的知識はもともとある程度あるし、前半の作図や構造図の座学で規準も頭に入っている。最後の解説も多少駆け足になっても理解するはず。』と見込んで、一台の検査時間は60分としました。
![IMG_3886[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/11/IMG_38861-300x225.jpg)
今回は7人を2〜3人の3班に分け、午前午後2台ずつ、各チーム内単独行動ナシで相談しながら巡行してもらいました。
![IMG_3897[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/11/IMG_38971-300x225.jpg)
『間違い探し』ではなく、あくまで『配筋検査』なので、まず地道に各部位に鉄筋が構造図通りの種類、本数、サイズのモノが入っているか確認することから始めます。
講師は基本的に口出ししません。
「ココがこう違ってますよね?」と聞かれればイエス/ノー、あとはくまなく残さずモックアップを見るためのナビ役です。
『これで5つ見つけたか。あといくつだなー』と思って横にいるとついヒントを出したくなりますが、多少はガマンします。
![IMG_3898[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/11/IMG_38981-300x225.jpg)
なんか周りが騒々しい、と思っていたらひどい豪雨に。川越の東日本RCでの台風21号くずれの大雨並みです。
![IMG_3891[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/11/IMG_38911-e1573634966476-225x300.jpg)
今日は朝から割といい天気でしたが、ずっとこの屋内にいたので天候の変化に気付きませんでした。今日の大阪は天気が不安定みたいです。
お昼をはさんで3時まで、モックアップ検査実習は続きました。
![IMG_3883[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/11/IMG_38831-300x225.jpg)
最後に答え合わせです。本当ならグループごとに発表してもらう予定でしたが、帰りの新幹線の時間もあり、一挙解説となりました。
どの班も、8割ぐらいでしょうか、各モックアップの指摘箇所を見つけたようです。残した2割がいい勉強になります。
何とか予定通りに西日本RCでの一日研修を終えました。
担任は検査用のバインダーなど宅配で別送手配の後始末があったので一人居残りました。ところがみんなを見送った直後に再度激しい雷雨に見舞われ足止め。結局遅れること小一時間、遅い新幹線で帰る羽目に。
おみやげに551蓬莱のチルド豚まんが買えたのがせめてもの慰みでした。
さて明日はみんな元気に出てくるでしょうか?
2019年11月11日 10:24 PM |
カテゴリー:令和元(2019)年度鉄筋コース
11月8日(金曜日) 訓練20日目

作図実習も6日目に入りました。
本日の専門講師は、ダイニッセイの阿部講師です。
鉄筋の施工図も、建物の設計図と同じく「平面図」「断面図」「立面図」に似た感じで、X、Y、Z軸に切った図面を描きます。

今まで行ってきた作図第一クールはX軸に相当し、今日までの予定で描いている第二クールの図面はY軸に切ったものになるわけですが、実際に現場での組立、あるいは鉄筋加工場での材料加工、さらにさかのぼって鉄筋の積算に供するには、施工図はそれぞれの柱や梁といった部材ごとにX・Y・Zをセットにしてやる必要があります。
豚肉・玉ネギ・長ネギをそれぞれ下ごしらえした後で、一本ごとに「串刺し」するような感じです。
これを「取付帳」といいますが、この鉄筋コースの作図実習は、取付帳の作成がCADでできるレベルにまで到達させることが目標です。
今日は第二クールをほぼ全員が終えたところで、いったん一連の訓練の流れからちょっと離れて、この「取付帳」を単品で作成してみることにしました。
あくまで目的指向で図面を表現してやることが重要です。
図面がコミュニケーションの道具である以上、不足のない情報を解りやすく盛り込んでやることが重要で、また逆にマニアックな表現もここでは不要なのです。
川上から川下へ、必要な情報を形を変え、しかも漏らさず流してやる、そんなことを念頭に訓練を行っています。

早いもので今日で訓練は3分の2が終了です。
明日は本コース初の土曜休日、そして来週月曜は朝から大林組「西日本ロボティクスセンター」で、実大モックアップによる配筋検査研修です。
そのため大阪に自宅がある訓練生などは今晩から大阪へ移動、2日の休日のあと月曜は1日みっちり研修して夜東京に戻ります。
去年は日帰り弾丸ツアーでしたからそれよりはゆとりある行程ですが(その分終日みっちりやる)体調に留意して来週に備え体を休めましょう。
2019年11月9日 12:19 PM |
カテゴリー:令和元(2019)年度鉄筋コース
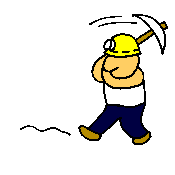
当ブログは即日更新を心がけておりますが、臨時の教材作成その他やむを得ない事由により、更新が滞ることがあります。(というか大体慢性的に滞っています・・・) 事務局の「働き方改革」にご理解をお願い致します。
2019年11月9日 12:00 PM |
カテゴリー:令和元(2019)年度鉄筋コース
11月4日(月・振) 訓練16日目
文化の日の振替休日です。
昨日とうってかわって朝からいい天気、晴れの特異日も振替のようです。
 完全隔週2日で開講している訓練校では今日も授業があります。 ちょうど31日の訓練の中日にあたります。
完全隔週2日で開講している訓練校では今日も授業があります。 ちょうど31日の訓練の中日にあたります。
今日の訓練内容は、先週前半に始めた計10日半のカリキュラムを組んでいる作図実習の3日目です。

今日の専門講師は、早川鉄鋼販売(株)から嶋村講師、(株)ダイニッセイから阿部講師に来ていただいています。
3つある作図課題グループの第1クールの最終日になります。 さすがに3日目になると一人一人の進度には差が出てきますが、みな夜も自室で復習や補習に励んでいるようで、一晩明けるとちゃんと予定日にゴールできそうなぐらい課題をこなしてきています。

講師の先生が入れる赤ペンをちょっと覗いてみましょう。

結構まだまだ、描けているようでも赤だらけ。 「キレイに描けている」=「何だか正しいみたい」という、CAD特有の陥りやすい錯覚です。 自分で描いておきながら、不完全な図面でも、描き込んでいくとつい出来上がったような気になります。

講義が終わり、今日の訓練報告を自分の会社に送ると今日の訓練は終わりで、みな部屋へ戻ります。 これはそのあとの講義室です。 何だかキレイな机の上。 その理由は、訓練生が全員ノートパソコンを自習のため部屋へ持ち帰っているからです。
ここで鉄筋コースも折り返し点を通過です。
2019年11月4日 7:59 PM |
カテゴリー:令和元(2019)年度鉄筋コース
11月に入りました。

今日から安全当番は、ベトナム出身のソン君。日本語はまだたどたどしいですが、よく通る大きい声で朝礼の司会をしてくれます。
当訓練校は「氷川神社前」というバス停にあります。
荒川の流域には氷川神社が多く、暴れ川を鎮めるために出雲から勧請したのだそうですが(島根県には簸川という川があります)、縁結びの神様でもあるらしく、まあいつもの仕事とちょっと違う縁を結ぶ訓練校のそばにあるには相応しいんじゃないかなと思い、毎日一日にはお参りしています。
今朝もお参りに行きましたら境内で地元のご老人にお会いしました。ニッカボッカをはいていて元は町鳶の親方だったそうです。御年95歳。 この辺は最近までしょっちゅう洪水にやられていたが、例の地下のパルテノン神殿ができてから一気に改善されてきたんだそうです。 町の消防団も長いことやっていて、かくしゃくとした生き字引みたいな方でした。 (こんど鳶コースで客員として登壇してもらおうかな?)
訓練14日目の今日からは、塩家講師による安全衛生教育が始まります。
塩家講師は、大林組在籍当時から安全部で社内の安全教育を担当され、現在も建災防などで資格講習などの教育にあたっておられます。
第一日目は、『安全衛生管理』と『リスクアセスメント』について学びます。

対面の講義形式でのインプット教育から始まりますが、メインはなるべく少人数でのグループワークで話し合いながら手を動かす研修スタイルです。
 何種類もある作業の災害予測訓練を行い、それを防ぐ方法を講ずるという、基本的にはKYの手法による訓練です。
何種類もある作業の災害予測訓練を行い、それを防ぐ方法を講ずるという、基本的にはKYの手法による訓練です。

職長役はテーマごとに交替して・・・

「立入禁止区画よし!」×3回コールして次のテーマへ
一人 ~ チームリーダー ~ チームメンバー ~ これの繰り返しが重要です。
2019年11月2日 10:24 AM |
カテゴリー:令和元(2019)年度鉄筋コース
10月31日(木) 訓練13日目。
今日は再び川越の大林組東日本ロボティクスセンターへ出かけます。
先週は台風21号の接近に伴う大雨に見舞われ大変でしたが、今日はまずまずの天気のようです。

本日の訓練は、午前が「揚重計画のチェックポイント」、午後が「玉掛けの安全教育」。計算や図表を使って、「自らが使う鉄筋材などを作業場所までどうやって動かすか?」を習得する一日です。
職長は、人を動かすのと同時に、モノを動かせないと仕事になりません。
ですから、クレーンとりわけ移動式クレーンの作業計画は大変重要な職能です。
今日の講師は、ロボティクスセンターの小林講師に午前・午後とも担当していただきました。
クレーンは、普段から皆現場でも工場でも使い慣れていますが、体系的に学ぶ機会はなかなか無く、知識を積み増しながら頭の中に整理できたようです。
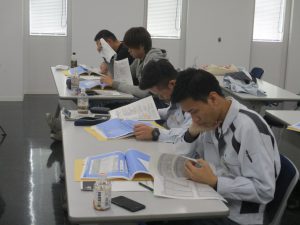
2019年11月1日 3:34 PM |
カテゴリー:令和元(2019)年度鉄筋コース
10月30日 (水) 訓練12日目
今日午前は作図実習2日目。専門講師は(株)小黒組の安藤講師です。
昨日のお2人とリレー型式で担当していきます。
今年の訓練生は、かなり持ち帰り率が高く、CADの作図スピードも全員だいぶ上がってきました。 これからが楽しみです。
午後は大林組構造設計部の平柳講師が登壇し、構造図とりわけ標準仕様書の見方について講義を行います。 今日と来週の半日2回分けになります。

この講義は例年、訓練生以外でも聴講希望のリクエストがあり、今年も(株)小黒組から1名聴講生が参加しました。
まさに今訓練生は作図課題で、この仕様書と対峙している真っ最中。今年は多分ベストのタイミングで、構造図を作成する立場の講師と、それを使って建物とかインフラなどの成果品を造る鉄筋工の訓練生との間での講義、ができたと思っています。
昨日、課題である『O計画』の設計図を、「質疑書をつくる」という問題意識を持って読んでおいてほしかったので、ヒントを与えた上で質疑書作成の宿題を出題しました。
訓練生は、みな自分の分かる範囲で質疑を作成してくれました。
講義がやや前倒しで終わったのを機に、みなの質疑をまとめて平柳先生と一問ー答、「私ならこれはOKですね」「うーんこれは実際どういう使われ方されているか次第ですが?」など非常に臨場感のある「質疑応答」タイムになりました。
鉄筋工の職長が、他の鳶工や大工の職長と違うのは、「建物品質についてみた時、職長はその最も下流に居ますが、それでいながら最上流に位置する設計者とのコミュニケーションが、質疑書とか配筋検査などで非常に機会が多い」ということです。
質疑をもらった設計者は「ムムっ・・・スルドい質問だな」
応答書を返された職長は「フーム、そこはこだわるとこなのか」
そして基礎梁の第一回配筋検査が『初デート』(いや、『ファーストスクラム』か?)
何回か後に、「この人にならまあ、任せられるかな?」とお互いなればベストですが、ならないかも知れません。「よいモノを造る」気概は同じだと思います。唯一違うのは、「経済性を考える両者の差」に尽きるでしょう。
いづれにしても、こういった相手と紳士らしさを保ちつつ時には激しいコンタクトを辞さない・・・鉄筋工の職長に求められるのは一種ラガーマンシップのようなものなのかも知れません。(by にわかファン)
2019年10月31日 3:17 PM |
カテゴリー:令和元(2019)年度鉄筋コース
10月29日(火)
訓練も今日で10日目です。今日からいよいよ作図実習が始まります。昨年は9日間をこの実習に充てましたが、専門講師の先生方とも協議して、今年は10.5日に増やしました。
今日は朝方雨降りだったため、体操と朝礼は講義室で実施しました。
 まず担任から課題の進め方と解説を行います。 7人の訓練生は、みなもちろん鉄筋工ですが、建築系も土木系も居ますし、仕事の経験も持っているスキルにやはり差があります。 ですから皆に同じ課題を与えてますが、その中で「最低限達成せねばならないゴール」と、「100%の最終ゴール」の2つを設けて、それぞれの能力に合った指導を行います。
まず担任から課題の進め方と解説を行います。 7人の訓練生は、みなもちろん鉄筋工ですが、建築系も土木系も居ますし、仕事の経験も持っているスキルにやはり差があります。 ですから皆に同じ課題を与えてますが、その中で「最低限達成せねばならないゴール」と、「100%の最終ゴール」の2つを設けて、それぞれの能力に合った指導を行います。
毎日、在京鉄筋工事会社からの専門講師、冒頭でCADパソコン教育を担当したオーク情報システムの講師、および担任講師が、個別指導に全員への解説を交えて指導していきます。

今日は作図実習の初日ということで、毎年訓練生を送り出していただいている(株)松伸さんが、訓練状況の視察と激励に午後来校されました。

差し入れを頂きましたので、急遽おやつのコーヒータイムを設け、ドリップコーヒーを15人分淹れて、午後のエナジーチャージとお約束の体操をみんなでやりました。
 今日1日は、訓練生たちも自分の能力とやらなければいけない事とのギャップを感じたようですが、このリフレッシュもあって最後まで元気な様子でした。 松伸さん、ありがとうございました。
今日1日は、訓練生たちも自分の能力とやらなければいけない事とのギャップを感じたようですが、このリフレッシュもあって最後まで元気な様子でした。 松伸さん、ありがとうございました。
さてでは、今日は質疑書の宿題をやってもらう事にします。 作図実習はトレースとは違います。主体的に図面を読み、設計者の意図を正しく理解して実物に反映させないといけません。鉄筋工にはもっとも重要なコミニュケーションスキルの一つです。
2019年10月30日 3:35 PM |
カテゴリー:令和元(2019)年度鉄筋コース
10月28日(月) 訓練10日目
鉄筋コースは3週目に入りました。

今週も先週に引き続き一般教養、工事機械の知識、安全、と盛り沢山。
そして訓練期間の1/3を占める鉄筋の施工図作図実習も今週からはじまります。
鵜飼講師の2日目は、『職長の役割』と『構造力学の基礎』。
現場で職長は何を要求されるのか? 鵜飼講師が今まで施工に携わってきた経験談を交えて今日も対話型式で講義は進みました。
構造力学での知識は、玉掛けや資材の仮置きなどいろいろな場面で応用できないといけません。
しっかり復習しておいてほしいと思います・
2019年10月28日 8:41 PM |
カテゴリー:令和元(2019)年度鉄筋コース
10月26日(土) 訓練9日目
今日から2日間は、我々講師陣の長老格である鵜飼講師が登壇し、スーパー職長としての一般教養を教授します。
第一日目は、『建築施工概要』と『建築関係法令』です。

建設の仕事に携わっていれば、同じ現場の他職種の仕事とか、自分の仕事に関わりのある法律とかは、うっすらと、まだら模様には分かってきますが、こういう機会にまだら模様を埋めてやる事が必要です。
先生からは講義に質問を小まめに挟んで、一方的にならないよう会話のように講義は進みます。
3時にはけんせつ体幹体操をやって、集中力をU Pさせつつ一日の座学を修めました。
2019年10月26日 8:51 PM |
カテゴリー:令和元(2019)年度鉄筋コース
« 新しい記事へ
古い記事へ »
![IMG_3881[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/11/IMG_38811-300x225.jpg)
![IMG_3892[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/11/IMG_38921-300x225.jpg)
![IMG_3886[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/11/IMG_38861-300x225.jpg)
![IMG_3897[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/11/IMG_38971-300x225.jpg)
![IMG_3898[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/11/IMG_38981-300x225.jpg)
![IMG_3891[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/11/IMG_38911-e1573634966476-225x300.jpg)
![IMG_3883[1]](http://www.kunrenko.com/blog/wp-content/uploads/2019/11/IMG_38831-300x225.jpg)
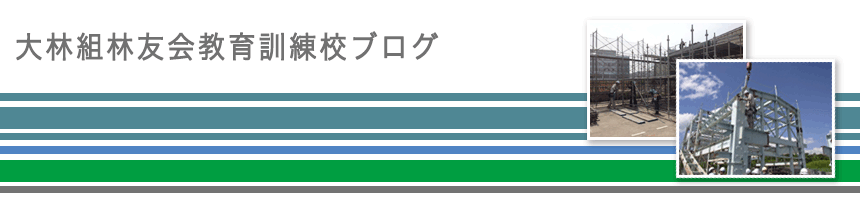



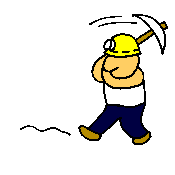
 完全隔週2日で開講している訓練校では今日も授業があります。 ちょうど31日の訓練の中日にあたります。
完全隔週2日で開講している訓練校では今日も授業があります。 ちょうど31日の訓練の中日にあたります。